人はなぜ予定を先延ばしにするのか
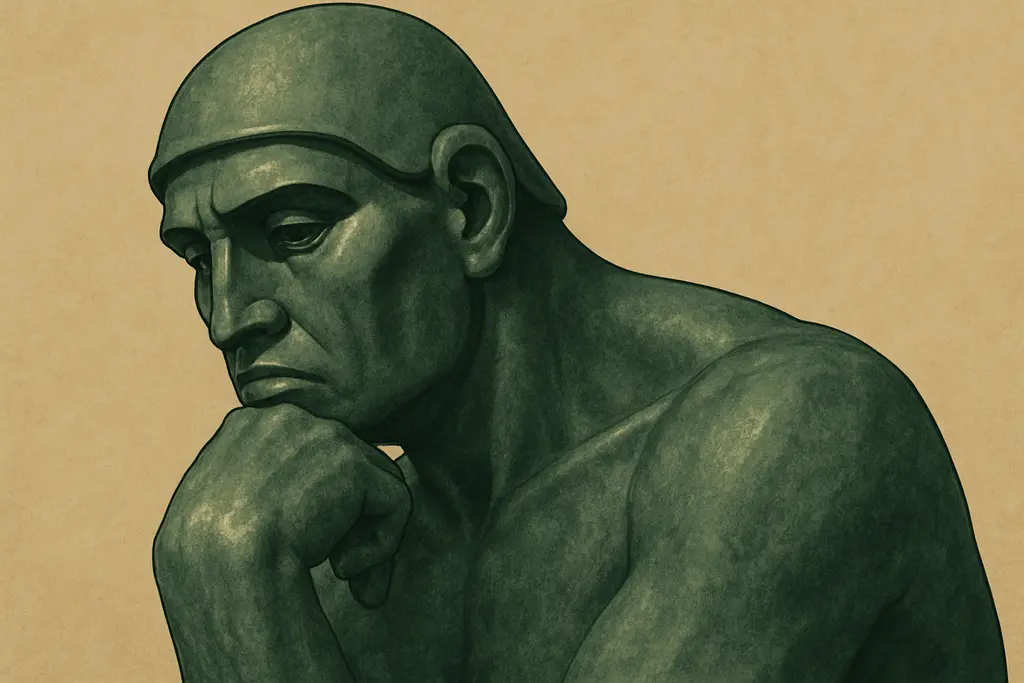
この記事では、ついつい先延ばしにしてしまうことについて原因を行動経済学の観点から解説します。
予定を先延ばしにしてしまうことって、日常でもよくありますよね。例えば
- ✓ 健康診断の予約をしなくちゃ
- ✓ あのお店のランチ、いつか行ってみたい
- ✓ 粗大ゴミ捨てたいけど面倒、まだ使えるしもうちょっと置いとくか
期限が決まっているものもあれば、いつやっても良いものまで様々です。
全てに共通することはいつかやると思っていること。
皆さんも、やろうやろうと思ってるのに数日・数週間・数ヶ月経ってしまった経験ありませんか?
すぐ行動すれば済むことなのに、なぜ人は先延ばしにしてしまうのか。
行動経済学の観点から考えてみたいと思います。
目次
原因
【現状維持バイアス】 Status Quo Bias
人は、今の状態を変えるよりも「とりあえずこのままでいいや」と考えがちです。
これを心理学・行動経済学では
現状維持バイアス(Status Quo Bias)
と呼びます。
たとえば「健康診断を予約しようかな」と思ったときでも、
- ✓ まだ体に不調はないし、急がなくても大丈夫
- ✓ 電話するのが面倒だから今日はやめておこう
と考えてしまうのは、現状を変えることに抵抗を感じる心の働きです。
なぜ現状維持を選んでしまうのか
-
損失を避けたい気持ち
変化による損の可能性を強く意識してしまう
-
意思決定の労力回避
選択・予約・行動にエネルギーが必要だから「後でいいや」と思う
-
慣れの安心感
現状を続ける方が安心で楽に感じる
この結果、「健康診断の予約をしない」「粗大ゴミをそのまま置いておく」といった行動に繋がります。
【双曲割引】 Hyperbolic Discounting
人は「今すぐ得られる小さな利益」と「将来得られる大きな利益」を比べると、つい今を優先してしまいます。
これを
双曲割引(Hyperbolic Discounting)
と呼びます。
たとえば健康診断。
「今すぐ予約すれば将来の安心につながる」と頭ではわかっていても、
- ✓ 今日は疲れているから後でにしよう
- ✓ 今やりたいことがあるから、予約はまた今度
と、将来の価値より今の価値を重視してしまうのです。
なぜ起こるのか
-
将来のことは実感が薄い
未来のリスクやメリットを軽く見積もってしまう
-
今の行動は感情に直結する
面倒さ・不安・快楽の方が強く影響する
-
短期と長期で判断基準が変わる
目の前だと即決、遠い未来だと先送り
その結果、「健康診断を予約すれば面倒がなくなる」という大きなメリットよりも 「今ちょっと楽したい」という小さな快適さを優先してしまいます。
【計画の誤謬】 Planning Fallacy
人は、自分の作業にかかる時間をつい
楽観的に見積もってしまう傾向
があります。
これを
計画の誤謬(Planning Fallacy)
と呼びます。
たとえば「健康診断の予約ぐらい、あとでサッとできるだろう」と考えてしまう。
しかし実際には、病院を調べたり、電話をかける時間を作ったり、日程調整をしたりと、思ったより手間がかかるものです。
その結果、「思ったより大変そうだから今日はやめておこう」と先延ばししてしまいます。
なぜ起こるのか
-
自分に都合よく予測する
過去の失敗や遅れを軽視してしまう
-
楽観バイアス
自分なら大丈夫、今回は早くできると思い込む
-
外部要因を見落とす
混雑状況や手続きの煩雑さを考慮しない
この錯覚のせいで、「やればすぐ終わる」と思いながら、実際にはなかなか着手できず、 気づけば何週間も経っている……という状況が生まれます。
【解釈レベル理論】 Construal Level Theory
人は、物事を
時間的・心理的に遠いか近いか
によって捉え方が変わります。
これを
解釈レベル理論(Construal Level Theory)
と呼びます。
- ✓ 遠い未来のこと → 抽象的に捉える(いつか健康診断に行かなきゃ)
- ✓ 近い未来のこと → 具体的に捉える(来週の水曜10時に電話をして予約する)
つまり、健康診断や粗大ゴミ出しのように「遠い未来でもいい」と思えるタスクは、 抽象的なまま放置されやすく、先延ばしにつながります。
なぜ先延ばしにつながるのか
-
抽象的だと行動に落ちにくい
「いつかやる」では動けない
-
緊急度が低く見える
「まだ先でいい」と感じる
-
未来の自分に任せがち
実際には“未来の自分”も忙しいのに、つい託してしまう
こうして、「そのうちやろう」が積み重なり、実際に行動するのがどんどん遅れてしまいます。
【選択オーバーロード】 Choice Overload
人は、選択肢が多すぎると逆に選べなくなるという現象があります。
これを
選択オーバーロード(Choice Overload)
と呼びます。
例えば、粗大ゴミを捨てたいと思っていても、
- ✓ 市の収集日に出す
- ✓ 指定の持ち込み場所に運ぶ
- ✓ 不用品回収業者に頼む
- ✓ フリマアプリで売る
…と方法が多いと、どれを選んでいいか迷ってしまい、結局「また今度にしよう」と先延ばしになります。
さらに厄介なのは「明日」という選択肢が生きている限り無限に存在することです。
「今日はやめて明日にしよう」と思えば、明日の明日、またその次の明日……と、際限なく後回しにできてしまいます。
なぜ先延ばしにつながるのか
-
選択のコストが増える
決めるだけでエネルギーを使う
-
失敗の不安が大きくなる
「他の選択肢の方が良かったかも」と考えて動けない
-
決断疲れ
日常で決断が積み重なると、重要な行動を後回しにしてしまう
こうして「決められない → 動けない → 放置」の流れが生まれます。
解決策
行動経済学の知見を活かして、ずるずる後回しを防ぐ具体的な方法を紹介します。
パワー・オブ・ビコーズ
予定を「なぜやるのか」とセットで書き込むことで実行率が上がります。
例「歯医者の予約 ― 早期発見の方がリスクが低いし安いから」。
この効果は、誰か他人へお願いする際に理由があった方が協力的になりやすいというものですが、
それを将来の自分自身へと置き換えています。
自律性バイアス
この効果は、誰かに決められたのではなく「自分」で決めたことに対してはやる気が起きやすくなるというものです。
予定を自分で立てることで、この効果が働き、行動に移しやすくなります。
しかし、誰かに決められる方が楽という人もいるので、その場合は自分の予定を誰かに作ってもらうのも一つの手です。
フット・イン・ザ・ドア
この効果は、小さなお願いから始めることで、
徐々に大きな依頼も受け入れてもらいやすくなる効果です。
これを自分自身に置き換えると、まずは小さな行動から始めると継続しやすくなります。
例えば、まずは予定名だけ入力してみる――
最初の一歩を低く設定することで、自然に次の行動へとつながります。
今日から試してみませんか?
予定を入力してみる